Title : Chapter 1 : Origin of System Dynamics
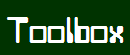
|
Location : Home > Methods > Simulation > SD > Introduction to System Dynamics Title : Chapter 1 : Origin of System Dynamics |
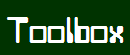 |
Origin of System Dynamics
Jay W. Forrester and the History of System Dynamics*1
システムダイナミクスは、マサチューセッツ工科大学(MIT)のフォレスター教授(Professor Jay W. Forrester)により1950年代半ばに提唱された。フォレスター教授が最初に MIT に来たのは1939年、電気工学科の学生としてであった。

最初、フォレスターが従事したのは MIT の自動制御ラボ(Servomechanism Laboratory)の創始者である、ブラウン博士(Professor Gordon Brown)の指導の下であった。当時の MIT 自動制御ラボのメンバーは、軍の装備のためのフィードバック制御の研究に携わっていた。第2次世界大戦中のラボにおけるフォレスターの担当には、空母レキシントンの装備された水圧制御レーダーシステムの修理のための太平洋戦域への派遣も含まれていた。レキシントンはフォレスターの乗船中に魚雷攻撃を受けたが沈没はしなかった。*2
WHIRLWIND I and SAGE
戦争終結後、彼は合衆国空軍のために航空機のフライト・シミュレータの開発に取りった。ディジタルコンピュータによるシミュレータの設計は行われたが、試験されることはなかった。しかしながら、シミュレータに関するブレーン・ストーミングの過程でコンピュータ化された戦闘情報システムの試験のほうがより適切な技術の適用であることが明らかになった。1947年に MITディジタル・コンピュータラボ(MIT Digital Computer Laboratory)が設立され、フォスターが管轄することとなった。このラボの最初の課題は、最初の戦闘情報システムの制御に効果的に利用できるか否かを確認する環境として、MIT初の汎用ディジタルコンピュータ WHIRLWIND I を開発することであった。WHIRLWIND I プロジェクトの一成果として、フォレスターは電流一致ランダムアクセス磁気メモリ(coincident-current random-access magnetic computer memory)を発明し、特許を取得した。これは約20年間にわたり産業用コンピュータメモリの標準となった。WHIRLWIND I プロジェクトによりフォレスタは実際的な機械のディジタル制御技術の確立への動機を高めた。
WHIRLWIND I プロジェクト終了後、フォレスターは、北アメリカ SAGE(Semi-Automatic Ground Environment)防空システムのためのコンピュータの開発に取り組むリンカーン・ラボ(Lincoln Laboratory)を率いた。SAGEプロジェクトの間にフォレスターのチームが開発したコンピュータは1950年代後半に実装され、約25年間にわたり機能し、 99.8% という顕著な稼動可能率を示した。
System Dynamics
このオンラインブックにとって、WHIRLWIND I 及び SAGE プロジェクトの成果としてもっとも注目すべきものは、おそらく、企業経営者が直面する困難に対するフォレスタの評価である。フォレスタは、管理者としての経験により、進歩を妨げるものは産業の問題の技術的側面からではなく、管理的側面から来ると結論付けることができた。
これは、フォレスターが社会システムは物理システムよりも理解と制御が困難であると認識していたからであった。1956年にフォレスターは新しく創設されたMIT経営大学院(MIT School of Management)で教授となった。フォレスターの最初の目標は科学・工学分野における彼の実績を、企業における成功や失敗を決定する主要な問題に関する問題に何らかの有用な方法で適用することであった。
後にシステムダイナミクスの成立に導くことになる、工学及び経営の双方に潜んでいる共通基盤に対するフォレスターの直感は、1950年代半ばにおけるジェネラル・エレクトリック社(General Electric)の経営陣との広範な範囲の関係が引き金となった。当時GE社経営陣はケンタッキーにある電気製品工場における雇用が明らかに3年サイクルを示していることに当惑していた。ビジネスサイクルによるものだとしても、それは雇用不安定に対する不十分な説明にしかならなかった。
実際の雇用・解雇に関する企業の意思決定構造を含むGE工場のストック=フロー=フィードバック構造を手計算で確認し、フォレスターはGEの雇用不安定性が企業の内部構造によるもので、ビジネスサイクルのような外部的な力によるものでないことを示すことができた。これらの手計算がシステムダイナミクス分野の端緒となった。
1950年代後半から1960年代初期にかけて、フォレスター及び彼の研究室の大学院生たちのチームはシステムダイナミクス分野の確立に注力し、手計算の段階からコンピュータモデリングの段階に移行した。リチャード・ベネット(Richard Bennett)が最初のシステムダイナミクスモデル言語 SIMPLE (Simulation of Industrial Management Problems with Lots of Equations)を1958年の春に提唱した。1959年にはフィリス・フォックスとアレクサンダー・プック(Phyllis Fox and Alexander Pugh)が、SIMPLEの改良版であるDYNAMO(DYNAmic MOdels)バージョン1を書いた。これはその後30年以上にわたり工業分野での標準となったシステムダイナミクスモデル言語*3である。フォレスターは工業ダイナミクスの分野における最初の、そして今でも古典となっている、著作を1961年に著した。*4
Urban Dynamics
1950年代後半から1960年代後半にかけて、システムダイナミクスは、もっぱら企業や経営の問題に対して適用された。しかしながら1968年、予期せぬできごとが企業モデリングの範囲を大きく超えて現れた。ボストン元市長のジョン・コリンズ(John Collins)がMITの都市問題(Urban Affairs)の客員教授に任命された。コリンズは1950年代の間ははポリオに悩まされており、エレベーターのところまで自動車でアクセスできるビルにあるオフィスを探していた。偶然にもフォスターのオフィスはそのようなビルにあり、隣のオフィスが空いていた。コリンズはこのようにしてフォレスターの職場の隣人となり、2人は都市問題について定期的に話をし、システムダイナミクスがこの問題にどのように寄与できるかを議論するようになった。
2人の共同研究の成果は『Urban Dynamics』という著作*5に結実した。この著作で示されたアーバンダイナミクスモデル(Urban Dynamics model)はシステムダイナミクスにとって初めての企業以外への適用例*6であった。しかしながらこのモデルは大いに議論を招いたし、今でもそうである。というのもそのモデルが多くのよく知られた都市政策が効果がないかさらに問題を悪化させることを示したからである。さらにモデルは直感に反した政策−例えば一見して誤っているとわかる政策−が驚くほど効果を示していたからである。例えばアーバンダイナミクスモデルでは、低所得者用住宅の建設は都市を停滞させる貧困のわなを生み出す一方で、建設を抑えれば雇用が創出され、都市住民の生活水準が向上する、という結果だったのだ。
World Dynamics
システムダイナミクスの企業以外への2つめの主要な適用は、1つめの成果から間もなくもたらされた。1970年にフォレスターはローマクラブ(Club of Rome)主催のベルンにおける会合に招待された。ローマクラブは人類の難問(predicament of mankind)と彼らが呼ぶもの、すなわち将来のいつか、世界的な危機が、すなわち指数的に膨れ上がる世界人口が地球の環境容量(再生可能/再生不能資源と廃棄物の処理) を追い越してしまう状況が発生するという問題を解くべく集められた組織である。ベルンの会合においてフォレスターは人類の難問にシステムダイナミクスは答えることができるか、と問われた。彼の答えはもちろん、できる、だった。
ベルン会合からの帰りの飛行機の中でフォレスターは世界の社会経済システムのシステムダイナミクスモデルの最初の草案を作成した。彼はこのモデルを WORLD1 と呼んだ。合衆国への帰る途中に、フォレスターはローマクラブのメンバーが MIT を訪問するのに備えて WORLD1 を洗練した。フォレスターはこの改良したバージョンを WORLD2 と呼んだ。このモデルを基に、フォレスターは『ワールドダイナミクス(World Dynamics)』*7を著した。
最初から、ワールドダイナミクスは大きな注目を集めた。WORLD2 モデルは世界人口・産業生産・汚染・資源と食物の間の重要な相互関係をマッピングしていた。モデルは、もし地球の環境容量を超えるような需要を削減するステップが取られなければ、21世紀中に世界の社会経済システムは崩壊するということを示していた。モデルはグローバルシステムをより高品質な状態にすることを可能にする政策変更を特定するためにも用いられた。
『ワールドダイナミクス』の評判に対し、ローマクラブはシステムダイナミクスによる人類の難問に対する拡張的研究への資金拠出を申し出た。しかしフォレスターはその時、アーバンダイナミクスプロジェクトの拡張に取り組もうとしており、参加を断った。しかしながら、博士課程の学生の一人−デニス・メドウス(Dennis Meadows)−に研究を行うよう示唆した。メドウスとその共同研究者がこのとき作成したモデルは WORLD3 と呼ばれ、『成長の限界(The Limits to Growth)』として発表された。WORLD3 モデルは WORLD2 よりいっそう精巧であったけれども、計算結果は同じ行動様式を返し、前バージョンモデルと同じ重要なメッセージを示していた。このような結果の類似性にもかかわらず『成長の限界』は『ワールドダイナミクス』よりも広範に世界から注目を集めた。これは専門的な知識をもたない読者でも読みやすいようなスタイルで書かれたという理由もあったかも知れない。*8
1991年に、『成長の限界』の原著者3人が出版20周年を記念して研究をやり直した。
その結果は『限界を超えて(Beyond the Limits)』*9として出版された。この研究のために修正されたモデルは WORLD3-91 と呼ばれている。
『限界を超えて』で提出された結果はオリジナルの研究がなされた時点では存在していなかった重要なデータが含まれていたが、『ワールドダイナミクス』や『成長の限界』で提出された結果と一貫していた。また『限界を超えて』では、先立つ2つの本に向けられていた批判に反論する内容も含まれている。
The System Dynamics National Model and K-12 Education
最近の20年間は、フォレスターの興味は主に次の2つの分野に向けられていた。すなわち合衆国経済のシステムダイナミクスモデルの構築と幼稚園から高校までにおけるシステムダイナミクス教育の拡張である。
前者のプロジェクトについてフォレスターは経済科学とマクロ経済システムがどのように機能するかに関する基礎的な理解に対する新たなアプローチとなるとみなしている。また後者のプロジェクトについてはシステムダイナミクスの分野の将来を健全なものとするためだけでなく、人間社会の未来の健全さにとっても重要であると見ている。
フォレスターの国家経済モデルは未完成な状態ではあるが、その中間成果は発表されている*10。顕著な成果としては、モデルが40年〜60年の経済サイクルや1930年代の大恐慌を説明するだけでなく、深刻な経済不況が資本主義社会の反復的な事象であることを示したことである。本稿執筆時点では、フォレスターのモデルは合衆国経済が長い下降傾向から脱した状態であることを示している。
フォレスターによるシステムダイナミクスの K-12 教育への拡張の努力は、彼のMITでの恩師であるゴードン・ブラウン(Gordon Brown)から物語が始まる。
ブラウンは1973年にMITを退職して、アリゾナ州のツーソンで暮らし始めた。1980年代後半、ブラウンはツーソン(Tucson)教育システムの教師にシステムダイナミクスを紹介した。結果は注目すべきものであった。システムダイナミクスは紹介された最初の中学校だけでなく、学区の全学校に広まった。今日ではシステムダイナミクスは、シェークスピアや経済学・物理学と同じくらいよく教えられる教科となっている。さらに地区自体も、学習する組織*11への努力をシステムダイナミクスを用いて検討している。
K-12 教育におけるシステムダイナミクスの将来は有望である。今日では、システムダイナミクスの K-12 教育のための、国際的な教材の一覧が存在し、インターネットや WWW で情報を広く収集することもできる*12。合衆国だけでなく海外の多くの K-12 教育者がシステムダイナミクスを授業に取り入れ、このテーマに関する国際会議にも出席するようになった。このような状況は、将来の企業や公的機関の意思決定者が、システムダイナミクスの視点を通して問題を把握するようになることを示唆している。*13
【原注】
[Previous] |
[Next] |
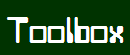 |
Updated : 2006/01/28 |