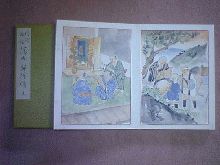
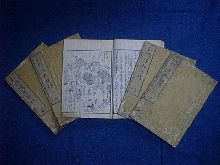
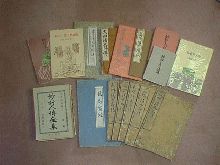
 大和清九郎に関する史料 2012.09.09 update
大和清九郎に関する史料 2012.09.09 update
| 年号 | 西暦 | 年齢 | 事暦 |
| 延宝6年 | 1678年 | 当 歳 | 大和国高市郡矢田村(現、高市郡高取町大字谷田)に出生す. |
| 幼 児 | 両親と共に丹生谷(現、高取町大字丹生谷)に転住、父を亡う. | ||
| 元禄15年 | 1702年 | 25才 | 赤穂義士の討入あり.(忠臣蔵) |
| 30才の頃吉野郡鉾立に移る. | |||
| 33才のとき女房を失い、その遺言に感じて仏法を信ず.3年あまりで又丹生谷に戻る. | |||
| 享保4年 | 1719年 | 42才 | 12月の法事に本山へ参り、布を寄進して襦袢一枚で帰国す. |
| 或る年の寒き頃、盗賊入りしに、清九郎の徳に感じて改心す. | |||
| 清九郎或年の暮、少ない田地の中から畑を光蓮寺へ寄進したが、娘の小万久六夫婦もこれを聞いて喜ぶ. | |||
| 娘小万26才で病歿す.婿久六その後、妻をめとらず養父清九郎と共に仏法を喜びたりと言う. | |||
| 元文3年 | 1738年 | 61才 | 早春、枯竹にて苗代に垣を結び、4月1日の東本願寺大門棟上に参詣して帰国す.その枯竹に芽を生じたりと言う. |
| 寛延元年 | 1748年 | 71才 | 春、越中へ下向す.茗荷原妙覚寺住職と同道帰国す. |
| 寛延2年 | 1749年 | 72才 | 春1月、3月の両度、「妙好人伝」の著者石見の学僧仰誓師、丹生谷鉾立峯の清九郎宅を訪う. |
| 寛延3年 | 1750年 | 73才 | 前年の秋に軽い中風にかかったが、春になり、田原本法貴寺村の法筵の席で再発す. 翌日久六等が竹輿で連れ戻る.8月4日午の刻、往生の素懐を遂ぐ. |
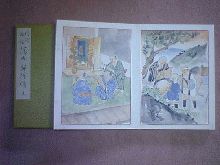 | 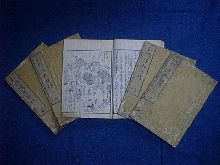 | 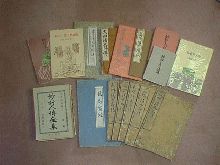 |
| 清九郎絵伝(上巻/下巻) | 和州清九郎伝(全5巻) | その他関連出版物類 |
|---|
また、川崎市に在住の喜多村氏のホームページにも史料の紹介があります。